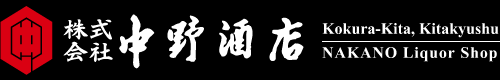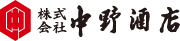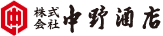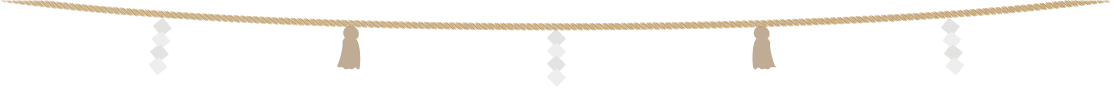
日本のお酒
 享保元年(1716年)、ご存知暴れん坊将軍の徳川吉宗が8代将軍に就任し享保の改革を始めた年、奥の松酒造は福島県二本松市で創業しました。あだたらで以前お話ししましたが、安達太良山の伏流水を使い、数々の名品を生んでいます。さて、今回はワイングラスで美味しい清酒を紹介しましょう。奥の松酒造の当主名から名づけた遊佐(ユサ)は、300年の歴史から培われた伝統の技と最新技術の融合による最良の酒造りを目指し、醸した純米吟醸酒です。爽やかな香りと飲み飽きしない旨みある味わいは、様々な料理との相性も良く、食中酒に最適です。日本酒度/-1.5、アルコール度/16、酸度/1.5ですから、北国の清酒にしては少し甘めで、ワイングラスで飲むのにグッドチョイスです。今日も1杯どうぞ!
享保元年(1716年)、ご存知暴れん坊将軍の徳川吉宗が8代将軍に就任し享保の改革を始めた年、奥の松酒造は福島県二本松市で創業しました。あだたらで以前お話ししましたが、安達太良山の伏流水を使い、数々の名品を生んでいます。さて、今回はワイングラスで美味しい清酒を紹介しましょう。奥の松酒造の当主名から名づけた遊佐(ユサ)は、300年の歴史から培われた伝統の技と最新技術の融合による最良の酒造りを目指し、醸した純米吟醸酒です。爽やかな香りと飲み飽きしない旨みある味わいは、様々な料理との相性も良く、食中酒に最適です。日本酒度/-1.5、アルコール度/16、酸度/1.5ですから、北国の清酒にしては少し甘めで、ワイングラスで飲むのにグッドチョイスです。今日も1杯どうぞ!
更新日時 : 2018年12月07日
カテゴリ : 日本のお酒
 明治24年(1891年)、 宮崎県えびの市で明石仁右衛門が焼酎の製造を始めて、127年になります。明治24年と言えば、ロシア帝国の皇太子ニコライが滋賀県大津町で巡査津田三蔵に切りつけられ負傷した大津事件があった年です。時の政府は大逆罪を適用し死刑にするよう圧力をかけましたが、大審院院長児島惟謙は刑法に外国皇族に関する規定はないとして一般人に対する謀殺未遂罪を適用し無期徒刑に処しました。司法の独立が護られ、日本が近代国家として認められるようになったという有名な事件です。このような明るい近代日本に貢献しようと、明石酒造は、代表銘柄明月を作りました。人々の心が満月のように、まあるく明るく円満に、そして平和にとの願いがこめられ、えびの高原に群生する赤松にかかる満月を表しています。南九州産さつまいも「コガネセンガン」を主原料に、白麹で仕込んだ芋焼酎に、米焼酎をブレンドすることにより、芋の香りを和らげ、ほんのりとした香りと口当たりのよい本格焼酎に仕上がりました。後味に残るほどよい絡み(苦み)がクセになる、大人の味わい「最高の切れ味」です。
明治24年(1891年)、 宮崎県えびの市で明石仁右衛門が焼酎の製造を始めて、127年になります。明治24年と言えば、ロシア帝国の皇太子ニコライが滋賀県大津町で巡査津田三蔵に切りつけられ負傷した大津事件があった年です。時の政府は大逆罪を適用し死刑にするよう圧力をかけましたが、大審院院長児島惟謙は刑法に外国皇族に関する規定はないとして一般人に対する謀殺未遂罪を適用し無期徒刑に処しました。司法の独立が護られ、日本が近代国家として認められるようになったという有名な事件です。このような明るい近代日本に貢献しようと、明石酒造は、代表銘柄明月を作りました。人々の心が満月のように、まあるく明るく円満に、そして平和にとの願いがこめられ、えびの高原に群生する赤松にかかる満月を表しています。南九州産さつまいも「コガネセンガン」を主原料に、白麹で仕込んだ芋焼酎に、米焼酎をブレンドすることにより、芋の香りを和らげ、ほんのりとした香りと口当たりのよい本格焼酎に仕上がりました。後味に残るほどよい絡み(苦み)がクセになる、大人の味わい「最高の切れ味」です。
更新日時 : 2018年11月23日
カテゴリ : 日本のお酒
1900年頃 明治政府は鹿児島の家庭での焼酎製造を禁止して、集落ごとで製造していました。江戸時代、薩摩阿久根は諸白(もろはく)と言った焼酎と国分煙草を生産していましたが、これらは薩摩藩を代表する銘品でした。その伝統を生かし、鹿児島ではやっと焼酎が販売されるようになり、販売を目的とした蔵ができてきます。この時代に合わせて登場したのが黒瀬杜氏の集団です。黒麹を使い従来の黄麹よりも質の良い焼酎を造ることで商業化がさらに進みました。麹米や仕込み方法にも改良を加え焼酎の品質向上が一気に進みました。鹿児島のみならず九州全域の蔵元から声がかかるようになり、杜氏集団はやがて300名を超える規模となります。その創世記に活躍したのが黒瀬金次郎であり、鹿児島酒造㈱黒瀬杜氏伝承蔵の総杜氏黒瀬安光は三男にあたります。 さて、鹿児島県産芋焼酎「粋鹿」(ろくすい)をご紹介しましょう。さつまいもは鹿児島県内の契約栽培、米麹は焼酎麹の育成に最適な水分量に仕上がる華麗米を使用しました。すべて鹿児島産の原料を吟味して使うことにより麹の働きが隅々まで行き渡り、麹米 ・酵母・さつまいもの特徴が遺憾なく発揮された完成度の高い焼酎に仕上がりました。これぞ薩摩いも焼酎の真骨頂です。
更新日時 : 2018年11月09日
カテゴリ : 日本のお酒