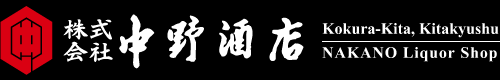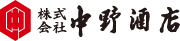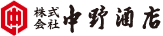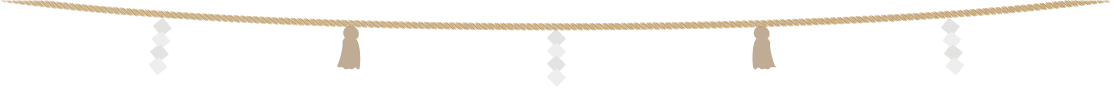
酒店日記
 ブラタモリの沖縄首里編を見ていましたら、次のような話がありました。江戸時代泡盛は江戸に多く運ばれ、大変人気があり、またアルコール度数の高い泡盛を振ると泡が盛ってくるので、泡盛と呼ばれるようになったそうです。嘉永元年(1848年)に誕生した瑞穂酒造は、現存する首里最古の蔵です。ブラタモリでもありましたが、首里はサンゴから生まれ、泥岩とサンゴから生まれた銘水が豊富です。その水と南方硬質米及び黒麹菌で仕込み、生まれたばかりの泡盛は、蔵の中で新たな熟成への眠りにつき、3年以上貯蔵した古酒(クース)として、長い年月を重ねるほど、まろやかで気品ある美酒へと変化していきます。太平洋戦争で首里が爆撃される前には300年を越す古酒があったそうです。さて、琉球泡盛古酒瑞穂43度は、キャラメルやナッツの様なほのかに香ばしい香りと心地よい甘みがあり、濃醇かつなめらかな口当たりが特徴です。加えて芳醇な風味の中には泡盛がもつ豊かな味わいと力強さを感じ、年数を経ることで、味わいと風味のさらなる熟成が期待できる泡盛です。古酒の風味を味わうのに、小さな盃でストレートまたはグラスでロックか水割りで飲むのがお勧めです。
ブラタモリの沖縄首里編を見ていましたら、次のような話がありました。江戸時代泡盛は江戸に多く運ばれ、大変人気があり、またアルコール度数の高い泡盛を振ると泡が盛ってくるので、泡盛と呼ばれるようになったそうです。嘉永元年(1848年)に誕生した瑞穂酒造は、現存する首里最古の蔵です。ブラタモリでもありましたが、首里はサンゴから生まれ、泥岩とサンゴから生まれた銘水が豊富です。その水と南方硬質米及び黒麹菌で仕込み、生まれたばかりの泡盛は、蔵の中で新たな熟成への眠りにつき、3年以上貯蔵した古酒(クース)として、長い年月を重ねるほど、まろやかで気品ある美酒へと変化していきます。太平洋戦争で首里が爆撃される前には300年を越す古酒があったそうです。さて、琉球泡盛古酒瑞穂43度は、キャラメルやナッツの様なほのかに香ばしい香りと心地よい甘みがあり、濃醇かつなめらかな口当たりが特徴です。加えて芳醇な風味の中には泡盛がもつ豊かな味わいと力強さを感じ、年数を経ることで、味わいと風味のさらなる熟成が期待できる泡盛です。古酒の風味を味わうのに、小さな盃でストレートまたはグラスでロックか水割りで飲むのがお勧めです。
なお、瑞穂はリニューアルされます。
更新日時 : 2016年02月28日
カテゴリ : 日本のお酒
 日本酒度の+数値が大きくなれば段々辛く、-数値が大きくなると段々甘くなるはずですが、酸度が増すと辛さ甘さが段々緩和されます。従って+18や-18であっても酸度を増せばそんなに辛くも甘くもなくなります。それにアルコール度数が加わるとコクが加わります。さらに、製法によって微妙な味わいが色付けされます。醸造酒は生き物ですから、完全に一定ということはありえず、杜氏さんはその舌と感覚で、平均値を飲み手に喜ばれる作品にしようと日夜励んでいます。さて、大分県国東(くにさき)半島・宇佐地域は世界農業遺産に認定されていますが、その国東にある萱島酒造2代目米三郎は、明治20年代に西は西日本、関は大関(当時は最高位、今の横綱)の意味で西日本の代表酒になりたいと西の関と命名しました。その後、中村千代吉、息子繁雄、そして河野日出男、平野繁昭の名杜氏の集積が西の関手造り純米酒です。国東六郷の山々に湧き出る名水と豊穣の地で育つ美味しい八反錦とヒノヒカリというお米を原料に、代々受け継がれる職人の技で丁寧に仕込まれています。日本酒度-1.5、酸度1.4と中口ながらやや甘めと言えましょう。まろやかな膨らみを持つ、米本来の芳醇タイプのお酒です。ひや、あるいはぬる燗でお召し上がりください。
日本酒度の+数値が大きくなれば段々辛く、-数値が大きくなると段々甘くなるはずですが、酸度が増すと辛さ甘さが段々緩和されます。従って+18や-18であっても酸度を増せばそんなに辛くも甘くもなくなります。それにアルコール度数が加わるとコクが加わります。さらに、製法によって微妙な味わいが色付けされます。醸造酒は生き物ですから、完全に一定ということはありえず、杜氏さんはその舌と感覚で、平均値を飲み手に喜ばれる作品にしようと日夜励んでいます。さて、大分県国東(くにさき)半島・宇佐地域は世界農業遺産に認定されていますが、その国東にある萱島酒造2代目米三郎は、明治20年代に西は西日本、関は大関(当時は最高位、今の横綱)の意味で西日本の代表酒になりたいと西の関と命名しました。その後、中村千代吉、息子繁雄、そして河野日出男、平野繁昭の名杜氏の集積が西の関手造り純米酒です。国東六郷の山々に湧き出る名水と豊穣の地で育つ美味しい八反錦とヒノヒカリというお米を原料に、代々受け継がれる職人の技で丁寧に仕込まれています。日本酒度-1.5、酸度1.4と中口ながらやや甘めと言えましょう。まろやかな膨らみを持つ、米本来の芳醇タイプのお酒です。ひや、あるいはぬる燗でお召し上がりください。
更新日時 : 2016年02月24日
カテゴリ : 日本のお酒
 焼酎には、連続式蒸留でアルコール度数36度未満いわゆる甲類と単式蒸留でアルコール度数45度以下いわゆる乙類があります。乙類は本格焼酎とも言われます。甲類は、何度も蒸留を行うためアルコール純度が高くなり、原料本来の風味や味覚の個性は乏しくなります。従って、チューハイのベースやリキュールの材料、あるいはカクテルの際に用いられ、ジンやウオッカなどの代用品として使われることがあります。梅酒などに使われるホワイトリカーが典型です。一方乙類の本格焼酎は、基本的に1回のみの蒸留のため、原料本来の風味や旨み成分が生きていることが特徴です。伝統的な蒸留機内を減圧しない常圧蒸留が主でしたが、最近雑味を少なくするため、蒸留機内の気圧を低下させ低温での蒸留を行う減圧蒸留が導入されるようになりました。本格焼酎は、米、麦、芋、黒糖、そば、栗、ジャガイモ等いろいろな原料を使っているものがあります。さて、今回ご紹介するのは、地元城島(久留米市近郊)の池亀酒造が提供する流石(さすが)です。独自の低温減圧製法で、吟醸酒の酒粕を原料に仕込んだ吟香米焼酎です。そのフルーティな香りとはうらはらな、切れ味の良い淡麗辛口で、熟成したまろやかさがクセになります。ロック、ストレート、炭酸割り、レモンやカボス割り、色々なバージョンで楽しめます。
焼酎には、連続式蒸留でアルコール度数36度未満いわゆる甲類と単式蒸留でアルコール度数45度以下いわゆる乙類があります。乙類は本格焼酎とも言われます。甲類は、何度も蒸留を行うためアルコール純度が高くなり、原料本来の風味や味覚の個性は乏しくなります。従って、チューハイのベースやリキュールの材料、あるいはカクテルの際に用いられ、ジンやウオッカなどの代用品として使われることがあります。梅酒などに使われるホワイトリカーが典型です。一方乙類の本格焼酎は、基本的に1回のみの蒸留のため、原料本来の風味や旨み成分が生きていることが特徴です。伝統的な蒸留機内を減圧しない常圧蒸留が主でしたが、最近雑味を少なくするため、蒸留機内の気圧を低下させ低温での蒸留を行う減圧蒸留が導入されるようになりました。本格焼酎は、米、麦、芋、黒糖、そば、栗、ジャガイモ等いろいろな原料を使っているものがあります。さて、今回ご紹介するのは、地元城島(久留米市近郊)の池亀酒造が提供する流石(さすが)です。独自の低温減圧製法で、吟醸酒の酒粕を原料に仕込んだ吟香米焼酎です。そのフルーティな香りとはうらはらな、切れ味の良い淡麗辛口で、熟成したまろやかさがクセになります。ロック、ストレート、炭酸割り、レモンやカボス割り、色々なバージョンで楽しめます。
更新日時 : 2016年02月20日
カテゴリ : 日本のお酒